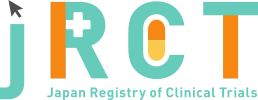臨床研究等提出・公開システム
再生医療等提供計画情報の詳細情報です。
| 第二種 | ||
| 令和6年12月16日 | ||
| 変形性膝関節症に対する自家脱分化脂肪(DFAT)細胞移植に関する臨床研究 | ||
| 変形性膝関節症に対するDFAT細胞治療の臨床研究 | ||
| 日本大学医学部附属板橋病院 | ||
| 吉野 篤緒 | ||
| 変形性膝関節症患者を対象として自家脱分化脂肪細胞(dedifferentiated fat cell: DFAT cell、以下「DFAT細胞」と称する)の関節腔内投与による細胞治療の安全性と有効性を評価する。 | ||
| 1-2 | ||
| 変形性膝関節症 | ||
| 募集前 | ||
| CONCIDE特定認定再生医療等委員会 | ||
| NA8160002 | ||
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
1 提供しようとする再生医療等及びその内容
申請者情報
申請者情報
| 令和6年12月15日 | |||
| jRCTb030240559 | |||
| 日本大学医学部附属板橋病院 | |||
| 東京都板橋区大谷口上町30-1 | |||
| 吉野 篤緒 | Yoshino Atsuo | ||
(1)再生医療等の名称及び分類
(1)再生医療等の名称及び分類
| 変形性膝関節症に対する自家脱分化脂肪(DFAT)細胞移植に関する臨床研究 | Clinical study of autologous dedifferentiated fat (DFAT) cell transplantation for knee osteoarthritis | ||
| 変形性膝関節症に対するDFAT細胞治療の臨床研究 | Cliniclal study of DFAT cell-based therapy for knee osteoarthritis | ||
| 第二種 | |||
| 膝関節の軟骨変性抑制、疼痛改善を目的として患者の体細胞(成熟脂肪細胞)を培養して得られる細胞を自家移植するため | |||
(2)再生医療等の内容
(2)再生医療等の内容
| 変形性膝関節症患者を対象として自家脱分化脂肪細胞(dedifferentiated fat cell: DFAT cell、以下「DFAT細胞」と称する)の関節腔内投与による細胞治療の安全性と有効性を評価する。 | |||
| 1-2 | |||
| 実施計画の公表日 | |||
| 2026年03月31日 | |||
| 5 | |||
| 介入研究 | Interventional | ||
| 単一群 | single arm study | ||
| 非盲検 | open(masking not used) | ||
| 非対照 | uncontrolled control | ||
| 単群比較 | single assignment | ||
| 治療 | treatment purpose | ||
| ① 同意取得時において年齢が18歳以上 ② 3か月以上続く慢性的な膝痛(ヒアルロン酸、PRP療法を含めた既存の保存加療に抵抗) ③ 立位単純レントゲンにてKL分類1以上の変形性膝関節症患者 ④ VAS40以上(両膝痛の方はVAS値が大きい方の膝を対象とし、VAS値が同一の場合、担当医師が判断した方に投与する) ⑤ 本研究への参加にあたり十分な説明を受けた後、十分な理解の上、研究対象者本人の自由意思による文書同意が得られた方 |
1. Age 18 or older at the time of consent 2. Choronic knee pain lasting more than 3 months. (Resistant to exsisting conservative treatments including hyaluronic acid or PRP therapy) 3. Patients with knee osteoarthritis with KL grade 1 or higher on standing sinple X-ray. 4. VAS 40 or higher (For patients with pain in both knees, the one with the higher VAS values will be targeted. If the VAS value are the same, the cells are administered th the one knee determined by the doctor.) 5. Patients who have received sufficient explanation using ICF and understand the contents, and who have obtained written consent to participate in the study group based on their free will. |
||
| ① 6か月以内の膝手術歴、3か月以内の膝関節注射施行歴のある患者 ② コントロール不良な糖尿病(HbA1C 8.0%以上)を合併している患者 ③ 悪性腫瘍を合併する、又は同意取得前5年以内の既往がある患者(但し、適切に処置された非黒色腫皮膚癌あるいは子宮頸部上皮内癌を除く) ④ HBs抗原、HBc抗体、HCV抗体、梅毒血清反応が陽性の患者 ⑤ リドカイン(キシロカイン®など)に対する重篤な過敏症、副作用の既往を有する患者 ⑥ コントロール困難な精神障害(認知症、アルコール依存症等)を合併する患者 ⑦ 妊婦、授乳婦、妊娠している可能性のある又は観察期終了時までに妊娠を計画している女性患者 ⑧ その他、実施責任者等が本試験の対象として不適当と判断した患者 |
1. Patients who have had knee surgery within the last 6 months or had intra-articular injections within last 3 months. 2. Patients with poorly controlled diabetes mellitus (HbA1C > 8.0%) 3. Patients with concomitant malignancy or a history of malignancy within 5 years prior to obtaining consent (except for appropriately treated non-melanoma skin cancer or epithelial carcinoma of the cervix). 4. Patients with positive HBs antigen, HBc antibody, HCV antibody, or syphilis serology. 5. Patients with a history of serious allergy or adverse reaction to lidocaine (e.g., Xylocaine). 6. Patients with psychiatric diorders that are difficult to control (dementia, alcoholism, etc) 7. Pregnant women, lactating women, and women who may be pregnant or plannning to become pregnant by the end of the observation period. 8. Patients who are deemed by the investigator to be unsuitable for participation in the clinical study. |
||
| 18歳 以上 | 18age old over | ||
| 上限なし | No limit | ||
| 男性・女性 | Both | ||
| [被験者毎の基準] 以下のいずれかに該当する場合は、個々の試験を中止する。 ① 同意取得後、被験者より中止の申し入れが(同意撤回等)があった場合 ② 本試験と途中で転院、転居等のため、本試験の継続が不可能となった場合 ③ 有害事象等発現のため、本試験の継続が困難であると判断された場合 ④ 移植細胞の品質不良等の問題により、移植が完遂できない場合 ⑤ 被験者の妊娠が判明した場合 ⑥ 登録後に適格基準を満たさないことが判明した場合 ⑦ その他、実施責任者等が本試験の中止を判断した場合 [試験全体の基準] 以下のいずれかに該当する場合は、本試験全体を中止する。 ① 特性細胞加工物の品質・安全性・有効性に重大な問題があると判断した場合 ② 実施責任者が、プロトコル治療の安全性、有効性に問題があると判断した場合 ③ 実施責任者が、論文や学会発表など本試験以外から得られた関連情報を評価した結果、プロトコル治療の安全性・有効性に問題があると判断した場合、又は試験継続の意義がなくなったと判断した場合 ④ 再生医療等提供機関の管理者もしくは地方厚生局長から中止の指示をうけた場合 ⑤ 実施責任者を含め、再生医療等提供機関の不適合により、適正な臨床試験実施に支障と及ぼしたと認める場合 |
|||
| 変形性膝関節症 | Knee osteoarthritis | ||
| 有 | |||
| 自家DFAT細胞を患者の膝関節腔内に注射する | Injection of autologous DFAT cells into the patient's kee joint cavity. | ||
| 安全性 ・有害事象の発現の有無 |
Safety: Occurrence of adverse events | ||
| 有効性 移植後4週、12種、24週の各時点における各種臨床スコアのベースラインからの変化率 ・VAS ・KOOS ・WOMAC |
Efficasy: Percentage change from baseline in various clinical scores (VAS, KOOS, and WOMAC) at 4, 12, and 24 weeks post-transplant. |
||
| 変形性膝関節症の患者から皮下脂肪組織を吸引採取し、細胞培養加工施設にて成熟脂肪細胞の培養を行いDFAT細胞を調製する。調製した自家DFAT細胞(1.5x10^7個)を症状のある膝に関節内注射する。移植後24週にわたり観察・検査を行い、安全性の確認と有効性の評価を行う。 再生医療等の内容を平易な表現を用いて記載したものは、別添の通り。 |
|||
2 人員及び構造設備その他の施設等
2 人員及び構造設備その他の施設等
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
(1)人員及び構造設備その他の施設に関する事項
| 医師 | |||||
| 中西 一義 | Nakanishi Kazuyoshi | ||||
| 日本大学 | Nihon University | ||||
| 医学部整形外科学系整形外科学分野 | |||||
| 173-8610 | |||||
| 東京都板橋区大谷口上町30-1 | 30-1, Ohyaguchikami-cho, Itabashi-ku, Tokyo | ||||
| 03-3972-8111 | |||||
| nakanishi.kazuyoshi@nihon-u.ac.jp | |||||
| 自施設 | |||||
| 日本大学医学部附属板橋病院救命救急センター(救急医療のために30床を確保) 同センターでは、X線透視装置、X線CT装置、MRI装置、経皮的心肺補助装置、人工呼吸器などが整備されている。 | |||||
(2)その他研究の実施体制に関する事項
(2)その他研究の実施体制に関する事項
| 松永 充博 | Matsunaga Mitsuhiro | ||||
| 日本大学 | Nihon University | ||||
| 医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 | |||||
| 173-8610 | |||||
| 東京都板橋区大谷口上町30-1 | 30-1, Ohyaguchikami-cho, Itabashi-ku, Tokyo | ||||
| 03-3972-8111 | |||||
| 03-3972-8666 | |||||
| matsunaga.mitsuhiro@nihon-u.ac.jp | |||||
| 医師 | ||
| 中西 一義 | ||
| 日本大学 | ||
| 医学部整形外科学系整形外科学分野(診療科:整形外科) |
| 医師 | ||
| 李 賢鎬 | ||
| 日本大学 | ||
| 医学部整形外科学系整形外科学分野(診療科:整形外科) |
| 医師 | ||
| 栁澤 正彦 | ||
| 日本大学 | ||
| 医学部整形外科学系整形外科学分野(診療科:整形外科) |
| 医師 | ||
| 張 英士 | ||
| 日本大学 | ||
| 医学部整形外科学系整形外科学分野(診療科:整形外科) |
| メディカルエッジ株式会社 | ||
| 上田 史郎 | ||
| メディカルエッジ株式会社 | ||
| 株式会社アクセライズ | ||
| 羽田 正英 | ||
| 株式会社アクセライズ | ||
| CRO事業部 | ||
| 株式会社アクセライズ | ||
| 高石 晴史 | ||
| 株式会社アクセライズ | ||
| 信頼性保証本部 | ||
| 日本大学医学部 | ||
| 谷口 哲也 | ||
| 日本大学 | ||
| 医学部一般教育学系数学分野 | ||
| 日本大学 | ||
| 松永 充博 | ||
| 日本大学 | ||
| 医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 | ||
| 松本 太郎 | Matsumoto Taro | ||
| 日本大学 | Nihon University | ||
| 医学部機能形態学系細胞再生・移植医学分野 | |||
| 該当 | |||
(3)多施設共同研究に関する事項
(3)多施設共同研究に関する事項
| 無 |
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物の製造及び品質管理の方法等
3 再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物の製造及び品質管理の方法等
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
(1)再生医療等に用いる細胞の入手の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 自家成熟脂肪細胞 | |
| 再生医療等の提供を行う医療機関と同じ。 | |
| 再生医療を受ける患者を細胞提供者として選定する(① 細胞提供者の健康状態、及び② 細胞提供者の年齢、は選択基準に準ずる)。 | |
| 再生医療を受ける患者の細胞を用いるため、再生医療を受ける患者の選択基準、除外基準と同じ。 | |
| 再生医療等提供機関において、穿刺予定の腹部に局所麻酔を施した後、チュメセント液(エピレナミン加2%キシロカイン溶液)を注入する。3〜4mm程度皮膚切開し、カニューラ付きシリンジを用いて脂肪5〜7 mLを採取する。創部はナイロン糸で縫合する。脂肪採取は、脂肪吸引術に熟練した形成外科医が行う。 |
(2)特定細胞加工物の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
(2)特定細胞加工物の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物を用いる場合のみ記載)
| 自家脱分化脂肪細胞(DFAT細胞) | ||
| (1) 細胞製造の方法 再生医療等提供医療機関より患者脂肪組織を受け入れ、コラゲナーゼ処理により自家脂肪細胞を単離後、天井培養による初代培養(P0)を開始する。規格に定める細胞数に到達するまで拡大培養(P1)を行い、回収・洗浄を経て凍結保存液に懸濁し凍結保存バッグに梱包し、最終製品とする。最終製品は細胞培養加工施設に設置された液体窒素タンク内で凍結保管する。 (2) 品質管理の方法 組織受入、細胞加工、取扱いの各プロセスで、以下に示す品質検査を実施する。 ①受入試験:脂肪組織の外観検査、輸送温度の確認 ②工程内管理試験:培地交換時、及び継代時に培養細胞の顕微鏡観察、細胞生存率測定を実施する。 ③規格試験:最終特定細胞加工物の細胞表面抗原確認検査として、フローサイトメトリーを用いて表面マーカー陽性細胞率が規格値を満たすことを確認する。最終特定細胞加工物(規格試験用の凍結保管品)に対して、無菌試験(日本薬局方一般試験法 無菌試験法)、エンドトキシン試験(日本薬局方一般試験法 エンドトキシン試験法)、マイコプラズマ否定試験(核酸増幅法)を実施し、すべて陰性であることを確認する。 |
||
| 最終特定細胞加工物 1 バッグを室温で融解し、シリンジに移した後、生理食塩水を加え、4 mLの細胞懸濁液とする。 再生医療等提供機関の外来処置室でエコーガイド下に患者の膝関節腔に注射する。 | ||
| 有 | ||
| 株式会社ロートセルファクトリー東京 | ||
| FA3150002 | ||
| RCFTプロセシングセンター | ||
| 脂肪組織の受入、DFAT細胞の製造、品質管理試験の実施、最終製品の出庫。 | ||
(3)再生医療等製品に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(3)再生医療等製品に関する事項(再生医療等製品を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
(4)再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項(未承認又は適応外の医薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載)
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
4 再生医療等技術の安全性の確保等に関す措置
(1)利益相反管理に関する事項
(1)利益相反管理に関する事項
① 再生医療等に対する特定細胞加工物製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
① 再生医療等に対する特定細胞加工物製造事業者からの研究資金等の提供その他の関与
| 株式会社ロートセルファクトリー東京 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
② 再生医療等に対する医療薬品等製造販売業者等からの研究資金等の提供その他の関与
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
| 無 | ||
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
③ 再生医療等に対する特定細胞加工物製造事業者又は医療品等製造販売業者等以外からの研究資金
| 無 | ||
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
(2)その他再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
| 本研究にて提供する特定細胞加工物(DFAT細胞)は、患者自身の皮下脂肪組織から単離した成熟脂肪細胞を天井培養することによって得られる細胞群であり、脂肪由来幹細胞(Adipose-derived stem cells: ASC)に類似した高い増殖能と多分化能を有する細胞である[Matsumoto T, Kano K, et al. J Cell Physiol 215:210-222, 2008]。本研究を統括する松本らの研究グループでは、DFAT細胞治療のFirst-in-Human臨床研究を実施し、これまでに4例の重症下肢虚血患者に自家DFAT細胞を移植しているが、細胞移植に係る有害事象は認められていない。本研究で提供するDFAT細胞は、製造方法の改良を行い、ウシ胎仔血清(FBS)が含まれる培地から動物由来成分が含まれない培地(ゼノフリー培地)に変更するなど、生物由来原料基準に適合したより安全性の高い方法で製造した細胞を用いる。この変更した製造法を用いて健常ボランティア脂肪組織から試験製造したDFAT細胞に対して、特性解析試験や各種安定性試験を実施した。収集したデータを基にPMDA相談(対面助言)を実施した結果、生物由来原料基準の対応状況、特定細胞加工物の貯法・有効期間の適切性、製造工程由来不純物及び副成分の安全性などについて、PMDAとの合意を得るに至った。また本製品の非臨床安全性試験として、軟寒天コロニー形成試験、核型解析、マウスを用いた一般毒性試験、免疫不全(NOG)マウスを用いた反復投与毒性試験・造腫瘍性試験を実施した。その結果、いずれの試験においても明らかな異常所見は認められず、本製品の移植安全性に特段の問題がないことを確認した。DFAT細胞を関節腔内に投与した実験では、移植された細胞は、主に滑膜に接着し関節腔内に局在することが確認された。また、他施設からの報告として、Poloniらは、ヒトDFAT細胞には、hTERT転写やテロメラーゼ活性亢進、非足場性増殖、染色体の構造異常は認められず、ヌードマウスへの移植実験にて腫瘍形成等の異常所見は認められなかったと報告している[Poloni A et al. J Cell Physiol 230: 1525-1433, 2015]。以上より、本研究にて提供するDFAT細胞は、十分な安全性が担保されていると考えられる。 | ||||||
| DFAT細胞は、ASCと共通の細胞表面抗原プロファイルを示すとともに、脂肪、骨、軟骨、平滑筋への多分化能を有し、国際細胞治療学会が定めた間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells: MSC)の最小基準を満たす[]。ASCに比べDFAT細胞は、①より少量の脂肪組織から高効率に大量調製できる。② 培養早期から均質な細胞が得られる。③ ドナーの年齢や基礎疾患に左右されず多分化能を有する細胞が調製できる、といった優位性がある[Matsumoto T, Kano K, et al. J Cell Physiol 215:210-222, 2008]。このような特長から、DFAT細胞はASC細胞治療が抱える「品質のばらつき」といった課題をクリアし、実用性の高い治療用細胞として期待できる。DFAT細胞は骨髄MSCやASCと非常に類似したサイトカイン分泌プロファイルを示し、これらの細胞と同等の免疫制御作用、抗炎症作用を有することを確認した[Kikuta S et al. Tissue Eng Part A 19:1792-1802, 2013]。Ohtakiら[Ohtaki M, et al. J Nihon Univ Med, 74:246-252, 2015] は、ラット軟骨欠損モデルに対してDFAT細胞から誘導した軟骨様組織を移植すると軟骨再生が促進されることを明らかにした。Endoら[Endo N, et al. Regen Ther 26:50-59, 2024]は、ラット変形性膝関節症モデルにDFAT細胞を関節腔内投与すると軟骨変性が抑制されることを明らかにした。そして、DFAT細胞が軟骨変性を抑制する機序として、DFAT細胞が滑膜線維芽細胞からのアグリカン分解酵素(Adamts4)の発現を抑制することなどを証明した。さらに、Fujiiら[Fujii S, et al. Rege Ther 21:611-619, 2022]は、膝蓋下脂肪体に由来するDFATは、膝蓋下脂肪体に由来するASCに比べ、軟骨分化能が高いことを示した。以上より、変形性膝関節症に対するDFAT細胞を用いた細胞治療は、既存先行しているASC細胞治療に比べても、同等以上の有効性が期待できる。 | ||||||
| 最終特定細胞加工物が規格試験項目の判定基準に適合し、再生医療等提供医療機関の実施責任者が投与可能と最終判断で決定した場合投与する。 | ||||||
| 実施責任者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病等の発生を知ったときは、「再生医療等安全性確保法」に従い、再生医療等提供機関の管理者及び研究代表医師、代表管理者を通じて規定の期間内に適切に厚生労働大臣及び認定再生医療等委員会へ報告を行う。報告は第一報(緊急報告)および第二報(詳細報告)とする。 なお、本研究は本細胞加工物を移植した状態で終了するため、個々の被験者の研究終了後、本細胞加工物に関する研究対象者に健康被害を及ぼすような新たな重要な情報が得られた場合には、研究対象者に対しその情報を伝え、必要な対応をとる。 |
||||||
| 本研究終了後10年間適切に保存する。 | ||||||
| 廃棄の方法として、本研究で得た試料は原則として、オートクレーブ処理の上、適切な方法で廃棄する。紙媒体の情報に関しては、シュレッダーで裁断し破棄する。その他の媒体の情報に関しては適切な方法で破棄する。 | ||||||
| 再生医療等を行う医師は、疾病等の発生を知った場合、速やかに実施責任者に報告を行う。実施責任者は、再生医療等提供機関の管理者(病院長) に報告する、報告の方法に関しては、日本大学医学部附属板橋病院が定める危機管理マニュアルに準拠する。 | ||||||
| 再生医療等を行う医師は、再生医療等の提供終了後、安全性及び科学的妥当性の確保の観点から、再生医療等(DFAT細胞治療)の提供による疾病等の発生、効果等について、被験者ごとに試験期間終了後は通常診療にて3年間の追跡調査に務める。また、疾病等の発生を知ったときは、必要に応じて、各種法令に従い報告を行う。 | ||||||
| 有害事象の収集は脂肪採取日から移植後24週までとする。有害事象は直接の観察(検査を含む)、被験者の自発的報告、または各来院時の被験者への質問によって確認する。被験者の連絡先、受診の状況などを常に把握し、必要があれば電話等で受診を促す。受診が困難な場合は、電話等による聴取を行い、有害事象の発現等について情報の把握に務める。 | ||||||
| 有 | ||||||
| 実施計画の公表日 | ||||||
| 募集前 | Pending | |||||
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
5 細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法
細胞提供者について
細胞提供者について
| 有 |
再生医療等を受ける者について
再生医療等を受ける者について
| 有 |
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
6 審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項
| CONCIDE特定認定再生医療等委員会 | COCIDE specified authorised regenerative medicine committee | |
| NA8160002 | ||
| 東京都千代田区二番町11番地3相互二番町ビルディング別館7階 | 11-3, NIban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo | |
| 03-5772-7584 | ||
| chiba@concide.or.jp | ||
| 第一種再生医療等又は第二種再生医療等を審査することができる構成 | ||
| 適 | ||
| 2024年12月03日 | ||
7 その他
7 その他
| 臨床研究実施に係る試料等を取扱う際は、実施責任者によって、個人情報とは関係ない研究用IDを付して管理し、研究対象者の秘密保護に十分配慮する。作成した対応表は、各参加施設の鍵のかかるロッカーで実施責任者が厳重に管理する。本臨床研究の実施に係る原資料類および同意文書等を取り扱う際は、研究対象者の秘密保護に十分配慮し、「再生医療等安全性確保法」および「個人情報の保護に関する法律」「実施施設の個人情報保護規定」 に準じて個人情報を管理する。病院外に提出する報告書等では、研究対象者識別コードを用いて匿名化して管理し、研究対象者の秘密保護に十分配慮する。また、本臨床研究の結果を公表する際は、研究対象者を特定できる情報を含めないように管理する。その他、本研究で得られた検体等を病院外に出す場合も匿名化し、研究対象者を特定できる情報を含めない。 詳細は、日本大学部附属板橋病院個人情報保護に関する運用管理内規に従う。個人情報の取扱いやその利用及び開示等については、省令を遵守し、実施する。 | ||
| 無 | No | |
| 提供機関管理者は再生医療等を適正に実施するために定期的に適切な教育又は研修の機会を確保する。 再生医療等を行う医師その他の再生医療等の提供に係る関係者は、内部研修の他、再生医療学会総会 (1回/年)、その他、再生医療等に関連する学会や研究機関が開催する講習会等に積極的に参加し、情報収集に努める。 |
||
| 診療科及び試験事務局に対応窓口を設置する。苦情や問合せを受けた場合、対応窓口の担当者はその内容を実施責任者及び研究統括者へ報告し、必要に応じて再生医療提供機関管理者である病院長へ報告する。 | ||
| 非該当 | ||
| なし | none | |
| 無 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
| 非該当 | ||
添付資料
添付資料
| 4 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式 | 4.同意説明文書_Ver 1.0 承認版_墨塗り版.pdf |
|---|